
中里の「楽満寺」から七沢の八坂神社方向に抜ける旧道(今は寸断されてほとんど消えて
いますが・・・)に「中里の道祖神」と呼ばれる場所があります。
「道祖神」は、主に昔の村の境界や道の辻、三叉路などに祀られている神で、村の守り神で
あり、子孫繁栄や旅の安全を守ってくれる神様として信仰されていました。
呼び方はいろいろあって、成田近郊ではドウロクジン(道陸神)と呼ばれることが多く、他にも
賽の神または障の神(サイノカミ)と呼ぶ地方もあります。


ここの「道祖神」には、数え切れないほどの小さな祠がうずたかく積まれています。
「道祖神」といえば、道端にポツンと立っているイメージですが、びっくりするような景色です。

鳥居は平成7年に建てられました。

手水盤の願主の数名の名前が読めますが、奉納の年代は読めません。


手水盤の脇に大正十一年(1922)の道標が立っています。
「此方 小野 大和田 滑河」と刻まれた面には、わざわざ「正面」とも刻まれています。
別の面二は、「此方 七澤 名古屋 ■■」、「此方 青山 倉水 成井 本大須賀」とあります。
今では目立たない脇道ですが、元々はここが人々の行き交う旧道だったようです。


***********

正面中央に周りのものより大きい、唐屋根に楓の紋が刻まれた祠があります。
明治三十二年(1899)のものです。


おびただしい数の小祠が並んでいる、というよりは積み上がっています。
人通りの無い小道の、それも大木の陰に・・・、この光景は怪しげですらあります。

***********

 道祖神と刻まれたもの・・
道祖神と刻まれたもの・・***********


文字は無いが祠の形


お札のような形や、さらに小さな形のものまでが混在しています。


積み上げられた小祠で、さながら塚のようになった裏側も、この景色です。


大部分は文字も刻まれていないものですが、丁寧に見て行くと、ほんのわずかですが年号が
記されているものがあります。
文化元年、文化四年、文化五年、文化十一年のものを見つけました。
ほとんどが文化年間(1804~1818)のもののようです。

中に一つだけ、奉納された常夜燈が崩れたのでしょうか、中央の祠の脇に置かれていました。
これまでにたくさんの道祖神を見てきましたが、そのどれにも無い、強く訴えかけてくるような、
「道祖神」群です。

幸町の三竹山道祖神(ドウロクジン)

東和田の道祖神

幡谷・香取神社脇の道祖神群

前林・妙見神社前の道祖神

吾妻・吾妻神社側の道祖神

堀籠・須崎神社の道祖神

押畑・新福寺下の道祖神(ドウロクジン)


*****

*********

*************

道祖神はタブの巨木の根元に積まれています。
このタブの木の推定樹齢は2~300年と言われています。
旧道の三叉路にタブの木が生えた小塚があって、ここに村人が「道祖神」を置き、何かに
つけて皆が小さな祠を奉納して行く内に、タブの木も大木になり、こんな不思議な光景に
なったのでしょう。
この道祖神群について唯一見つけた記録は、「下総町の社寺と石宮」(昭和60年)にある、
次のような記述です。
「道祖神 字原大間戸(一八一) 猿田彦命 足の悪い人が参拝する。また、現在三峰講は
ここを中心に行われる。」
あっさりした記述のため、これが「中里道祖神」のこととは気づきませんでしたが、巻末にある
古い写真は間違いなくこの鳥居とタブの木、そして積み上げられた道祖神群でした。

道祖神に刻まれた年号はほとんど文化年代(1804~1818)ですから、そのころはタブの木
もありふれた大きさの木であったはずです。
初めにここに小さな道祖神を奉納した村人は、200年後のこの景色を想像したでしょうか?
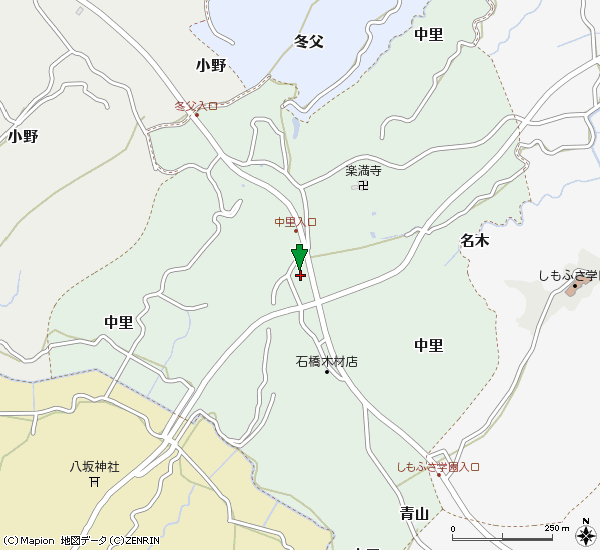
※ 「中里道祖神」 成田市中里181
今でこそ不気味にしか見えませんが、奉納数の多さは霊験あらたかな神として有名だったのでしょうね。
それもだんだんと薄れて行くのは仕方が無いことかも知れません。
今は鳥居を左に行く道しかありませんが、右に行く道が旧道だったようです。
ちょっと進むとこの道は途切れてしまいますが、昔はこちらを足が悪い人たちが
お参りにゆっくりと歩いてきたのでしょうね。


