今回は旧大栄町前林の「医王院」です。

「医王院」は曹洞宗のお寺で、山号は「前林山」。
500年近い歴史を持っています。

立派な山門は宝暦年間(1751~1764)のものとされています。
およそ260年の間、風雪に耐えてきました。

山門の脇には数基の石造物が並んでいます。

手前の石塔は天明二年(1782)のもので、 「三界萬霊等」 (等は異体字)と刻まれています。
この世のあらゆるものの霊を供養するという意味で建てられます。
一番高い石塔は明治三十三年(1900)の読誦塔で、「奉 讀誦普門品壱萬巻供養塔」と刻ま
れています。(普門品(ふもんぼん)とは「観音経」のことです)

こちらはちょっと変わったお姿の地蔵菩薩です。
右手に錫杖(欠損)を、左手には宝珠を持って蓮華座から左足を踏み下ろした半跏倚座を
とっている、ふっくらとした体型の力強い像形です。
右手が施無畏印を結ぶものもありますが、この像の右手は何かを握っていたような形です
から、立像が持つような長い錫杖ではなく、振り鳴らす短めの錫杖を持っていたのでしょう。
「享保二丁酉」 の紀年銘があります。
享保二年は西暦1717年ですから、300年前のものです。

これは、曹洞宗のお寺には必ずと言ってよいほど見られる「不許葷酒入山門」 と刻まれた
結界石で、“酒気を帯びたり、ニラのような臭いものを食べた者は、修業の妨げとなるので、
入山することを許さない”という意味です。
「安永七戊戌八月」 と刻まれています。(安永七年は1778年)
 高徳寺の結界石(堀籠)
高徳寺の結界石(堀籠) 養泉寺の結界石(東和泉)
養泉寺の結界石(東和泉) 長興院の結界石(伊能)
長興院の結界石(伊能) 宝応寺の結界石(伊能)
宝応寺の結界石(伊能)
「千葉縣香取郡誌」にはこの「医王院」について一行のみの記載があります。
「前林山醫王院 同村前林字門内に在り域内五百六十一坪曹洞宗にして藥師如来を本尊
とす」 (同村とは本大須賀村を指します)
「大栄町史通史編中巻」には、
「曹洞宗。前林村字門脇上に所在。山号は前林山(「郡誌」)。本尊は薬師如来(県寺明細」)。
常陸竹原(茨城県東茨城郡美野里町)の鳳林院の末寺。 鳳林院は多賀郡宮田(日立市)
大雄院の末寺であったから、大雄院-鳳林院-医応院という関係であった。天保十五年に
当寺が発行した寺送り状が今に残されている。(「史料編Ⅱ」〔一九〕)。明治三十八年に火災
に遭い、その後本尊を釈迦牟尼仏にしたという(「史話」)。」
(下線部の医応院は医王院の間違いです。)
(「史料編Ⅱ」とある寺送り状については、本項の最後に載せています。)
「医王院」という名前から、ご本尊は藥師如来だと思いがちですが、こちらは110年ほど前に
「釈迦牟尼仏」に替えようです。(市内の磯部にある真言宗の「医王院」や、茨城県龍ケ崎市
(曹洞宗)、横浜市金沢区(真言宗)、長野県南牧村(天台宗)等、多くの「医王院」のご本尊は
「薬師如来」となっています。)
「釈迦牟尼仏」または「釈迦如来」は、仏教の開祖の釈迦を仏様とした呼び名です。


昭和40年に建立された「招徳福」碑。
「開山曉天秀初大和尚 大永二年」と右側に記し、中央に「開創四百五十年之碑」と大きく
刻んで、左側には「開基前林志摩守 醫王院殿量外道無居士 天正六年三月二十九日
長蓁院昌安妙久大姉 天正六年五月廿七日」(蓁は異体字)とあります。
大永二年は西暦1522年、天正六年は1578年になります。
「大永町史通史編」中の「大須賀氏関連の中世城館跡」の項に、次のような記述があります。
「前林の地名は、すでに南北朝初期に「金沢文庫古文書」中に見られることから、鎌倉期
には集落が存在していたものと考えられる。 前林集落の大須賀川西対岸の字門内には、
曹洞宗医王院がある。 縁起によると、開山が大永二年(一五二二)、大檀那は天正六年
(一五六八)没の前林城主前林志摩守であったとされる。 この前林志摩守とは、消滅した
字城山の前林城に関連する大須賀氏一族の人物であろう。」
(下線部の一五六八は一五七八の誤りです。)
前林城は志摩守が没した12年後の天正十八年(1590)に、豊臣勢の攻撃で落城しました。

「招徳福」碑の隣には代々の住職の墓所があります。

本堂裏の山裾からはきれいな清水が湧き出しています。
地形的に豊富な水脈があるようです。

この石仏は風化と苔で年代は不明ですが、「地蔵菩薩」と刻まれているような気がします。

元禄九年(1696)の聖観音像。
きれいに苔が落とされています。
ちょっと余談ですが、この聖観音像が造られた元禄九年には、「竹島一件」と呼ばれる朝鮮
との領有権争いにより、竹島への渡航を禁止する措置が執られました。
現在韓国が「竹島」を自国領だと主張する根拠の一つに、この「竹島一件」を挙げていますが、
この頃「竹島」と呼ばれていて日本人の渡航が禁じられたのは、現在の「鬱陵島」のことです。
現在韓国によって占拠されている「竹島」は、この頃は「松島」と呼ばれていました。


**********

裏山の中腹に古い墓石が並んでいるのが見えます。
近づくと、天和、享保、安永、天明、寛政などの年号が読めます。
周りは鬱蒼と茂る木々に覆われて薄暗く、どの墓石も苔生しています。

苔で滑りそうな急坂があり、墓地はまだ上に伸びているようです。


**********

六地蔵が見守る山の上の墓地に出ました。
こちらは比較的新しい墓石が目立ちます。
境内に戻り、山門を出て緩やかな坂を100メートルほど行くと、鳥居の建つ三叉路になり、
そこにかつての「医王院」の痕跡が残っています。


**********


「愛宕神社」の鳥居の脇に、「延命瀧」と刻まれた明治三十年(1897)の石碑があり、手前の
岩から清水が滾々と湧き出しています。
ここはもともと「医王院」の敷地内で小さな滝があったそうです。
水量があり、水質も良いので、近隣の人々が毎日汲みに来ています。

「地蔵堂」の中のお地蔵様は年代不詳です。
ここにあった滝の名前からすると、「延命地蔵」でしょうか?
かつてはここが「医王院」の入り口だったのでしょう。

地蔵堂の横には数基の石造物が並んでいます。
*********

右端には年代不詳の「聖観音」。
*********

隣は「青面金剛」の庚申塔。
側面に「奉拜待庚申三年成就所」「惟時天明三癸卯十月庚申日」と刻まれています。
天明三年は西暦1783年で、大飢饉の真っ最中であったころです。
60日に1回、1年に6回ある庚申の日に人々が集まって、三尸の虫が天帝に悪口を告げない
ように夜明かしをする「庚申講」を、3年・18回続けると「庚申塔」を建てることができます。
*********

年代不詳の「聖観音」。
*********

「奉納大乘妙典六十六部供養塔」と刻まれた読誦塔。
「元文■未年」と読めます。
元文年間の未年は元文四年(己未・1739年)になります。
*********

寛政元年(1789)の「月待塔」。
「奉侍十・・・・・観世音」とあり、刻まれているのが聖観音ですから、欠損して読めない部分
には十五夜、十七夜、十八夜待のいずれかの文字が記されていたはずです。
*********

風化で何の像か、分かりません。
*********

「読誦塔」のようです。
元禄と読めるような気がしますが・・・。


「愛宕神社」への石段は急で、所々崩れていますのでちょっと危険です。
段数を数えながら登ったのですが、足許に気をとられて途中で数えられなくなりました。
100段以上はあるはずです。


大正十五年(1926)に建立された小さな石の祠です。
狭い境内には祠以外何もありません。

石段の最上段の左右に置かれている小さな石柱には、延享三年(1746)と刻まれています。



「延命瀧」碑と「地蔵堂」からは、「医王院」の境内がチラリと見えています。
500年の時の流れに、かつての広大な敷地も大分狭くなっていますが、それでも裏山の墓地
を含めれば相当な寺域が残っています。
近くには工業団地があり、大規模な採土場やソーラー施設など、開発の波がジワジワ寄せて
来ていますが、何とかこの静かな環境と歴史が続いていってほしいものです。
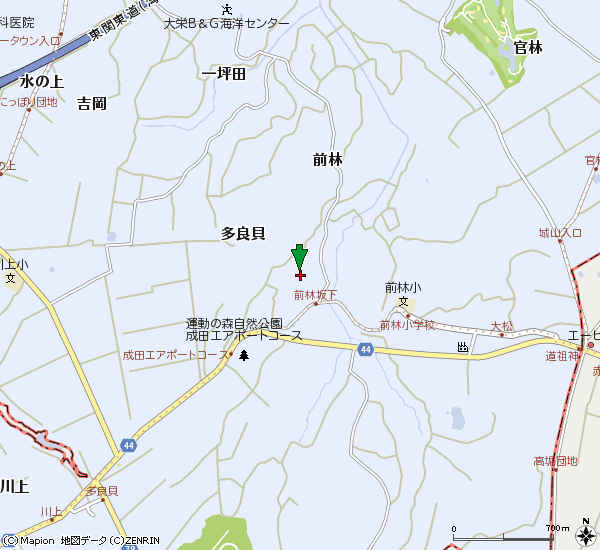
※ 「前林山 医王院」 成田市前林545
※ 「史料編Ⅱ」に収録の寺送り状(九八寺送り状)
寺送リ一札之事
一 此九八与申者、代々拙院檀中ニ御座候処、此度当人之依望寺送遣シ候間、然上ハ
何方之御檀中ニ相成候共、拙院ニ而ハ決而構無御座候、仍而寺送一札、如件
天保十五年 辰六月廿日
先御寺 様
前林村 醫王院
「九八」とは村人の名前です。
移住先が無いまま、寺送り状が書かれるのは非常に稀なことです。


