にあらためて取材に訪れました。

「観音寺」は珍しい「馬乗り馬頭観音」で知られています。

天台宗のお寺ですが、ほとんど資料がありません。
天台宗のホームページにも寺名と住所しか載っていません。

「香取郡誌」には、その他寺院の項にただ一行、「観音寺 天台宗 本尊・馬頭観音」とのみ
記載されています。
「山田町史」(昭和61年編さん)にも、簡単な説明があるだけです。
「観音寺 神生、向油田にある。本尊に馬頭観世音菩薩をまつる。下総七牧の一つ、油田牧
の内にあり、馬観音として信仰されてきた。」 (P1345)
ゼンリン地図には「観音寺」ではなく、「馬頭観音」と表記されています。

平成21年に掲げられた寺額には「馬頭観世音」と書かれています。

本堂の扉に空いた小さな窓から、御前立ちの「木像馬乗り馬頭観音」が見えます。
馬上で趺坐する姿は、後ろの厨子内に安置されている本尊と同じ像容と言われています。

**********

石段を登り、境内に入る場所に享和二年(1802)の石灯籠が立っています。
石灯籠の脇にある記念碑(平成二十一年三月の「馬頭観世音本堂修繕事業落慶譜」)には
次のように刻まれています。
『当山馬頭観世音は千数百年前(奈良、平安)の行基菩薩の作である。脇の貝塚は、早稲田
大学の調査チームにより三千五百年前の人骨が発掘され、旧茅場には実際に狩をした塚十
数ケ所あり、古代人の生活の営みがあった証である。 「向油田の馬頭観音」は馬体安全、
商売繁盛、家内安全の観世音として篤く信仰されて来ました。本堂は嘉永二年一月二十三日
の油田村の大火災で全焼し運び出された本尊は十七年間仮殿に安置される。明治五年三月
七日より九日迄、入仏供養の式が執行される。今も本堂展示物、二点に当時の焼けあとが
ある。本堂は慶応三年十一月二十八日大工上棟 明治元年三月十二日茅ぶき屋根上棟され
た。百五十年の月日による本堂の傷みも激しくなりよってここに本堂屋根と、本堂内の修繕、
仏具修復工事を奉賛し、以って馬頭観世音の壮大なる御慈悲を末永く仰がんとする。』
行基菩薩(ぎょうきぼさつ)とは、奈良時代の僧で、我国最初の「大僧正」となった行基のこと。
死後に朝廷より菩薩の諡号を授けられたため、「行基菩薩」とも言われています。
本尊の馬頭観音像が行基の作とすれば、実に約1300年前のものということになり、大変
貴重な文化財ですが、千葉県や香取市の文化財の指定ありません。
いわゆる「寺伝」だということなのでしょうか。


手水盤には天明三年と刻まれています。
天明三年は西暦1783年になります。



虹梁、木鼻等、どれも細かい部分にまでこだわった見事な彫刻です。



本堂の側面に郡馬の掲額があります。
右端には「馬乗り馬頭観音」が描かれていますが、本尊や御前立ちのように馬上に趺坐する
観音像とは異なり、馬に跨っています。
はっきりとは分かりませんが、肌は青く、三面六臂の忿怒相のような気がします。
「仏教における信仰対象である菩薩の一尊。観音菩薩の変化身(へんげしん)の1つであり、
いわゆる「六観音」の一尊にも数えられている。柔和相と憤怒相の二つの相をもち、日本では
柔和相の姿はあまり知られておらず作例も少ない。そのため、観音としては珍しい忿怒の姿
をとるとも言われ、通例として憤怒相の姿に対しても観音と呼ぶことが多いが、密教では、
憤怒相の姿を区別して馬頭明王とも呼び、『大妙金剛経』に説かれる「八大明王」の一尊にも
数える。」 (ウィキペディア 馬頭観音の項より)



馬の掲額は裏側の壁面上部にまで続いています。

境内の裏手斜面に四基の石造物が見えます。

左端の倒れかけた「馬乗り馬頭観音」。
風化が進み、紀年銘等は判読できませんが、馬に乗っていることは分かります。


隣に立つ「馬乗り馬頭観音」は右手に三叉、左手に未開の蓮を持ち、馬上に趺坐しています。
宝冠を被り、馬頭観音とは思えない柔和な顔つきです。
「安永六丁酉六月吉日」 と刻まれ、240年も風雨に晒されていたとは思えないほど風化が
少ない貴重な文化財です。(安永六年は西暦1777年)

右側の倒れた二基は「馬頭観世音」の文字のみが刻まれています。
地中に埋まっているため、紀年名は読めません。

この明治二十六年の読誦塔には側面に建立の経緯が記されています。
「維時明治廿五年八月於當山普門品読誦講ヲ創設シ二十六年九月ニ至満願成就ス依之
同十月廿七日是ノ大供養ヲ執行シ記名信徒ノ篤志ヲ■■■」


屋根には千葉氏の紋章、月星紋が光っています。
斜め左の上向きの三日月に一つ星の紋は、江戸時代中期以降に用いられたもので、それ
以前には上向きの三日月に一つ星でした。
 円通寺の月星紋
円通寺の月星紋ただ、寺社にある千葉氏の紋は九曜紋が圧倒的に多く、月星紋はあまり見かけません。
 西和泉の熊野神社
西和泉の熊野神社旧栗源町の真淨寺

 松子の寶應寺
松子の寶應寺

「観音寺」からちょっと下った三叉路に小さなお堂が見えます。
近づいてみると「虚空蔵菩薩」と書かれています。
「虚空とは、どこまでも広がる空間の意味で、広大無辺な仏の智慧と慈悲を象徴し、それが
母胎の中にあるかように優しく包み込まれている。虚空が決して破壊されないように、この
菩薩の智慧と慈悲も永遠不滅である。」 (「仏像鑑賞入門」 瓜生中 著 P104)


堂内には右手に宝剣を持ち、左手に如意宝珠を持つ立像の虚空蔵菩薩が安置されています。
ここに虚空蔵菩薩が祀られている理由は分かりませんが、お堂の周りはきちんと整理されて
いて、地元の人々に大切に守られている様子がうかがえます。

お堂の傍らに数基の石仏が並んでいます。



一基を除いていずれも「慈母観音」のようですが、ちょっと変わっているのが赤子に乳を飲ませ
ているポーズです。
慈母観音にはいろいろな像容がありますが、このような慈母観音は初めて目にしました。

一基だけ場違いのように立っているお地蔵様。
「奉 供養諸願成就」「寛政九巳十月吉日」 と刻まれています。
寛政九年は西暦1797年です。


東総地区に集中してある「馬乗り馬頭観音」は、他には木更津地区にしか無く、全国的にも
房総地方にしか見られないとされている珍しい石仏です。
山田町(現・香取市)は初めての取材でしたが、まだまだおもしろい石仏が隠れていそうです。
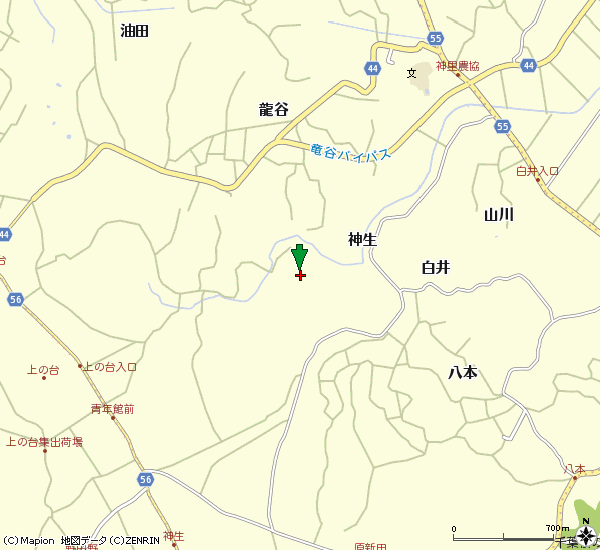
※ 「観音寺」(馬頭観音) 香取市神生1473-1
ご紹介下さる地域での「馬乗り馬頭観音」が重なり合って、ますます興味をかき立てられます。安永六年像の柔和さには、厳しい背景があったのでしょうが、思わず手を合わせたくなります。
放牧場があった関係で、馬にまつわる物語が数多く残され、馬頭観音
が他地域より多いように思われます。
旧街道の険しい坂道近辺では荷役に多くの馬が使われ、事故や過労
から死んだ馬を慰霊する馬頭観音が目立ちます。


